作品情報
原題:「I,Robot」
監督:アレックス・プロヤス
原作:アイザック・アシモフ『われはロボット』
出演者
ウィル・スミス(スプーナー刑事役)
ブリジット・モイナハン(カルヴィン博士役)
アラン・テュディック(サニー役 ※動作・音声)
ジェームズ・クロムウェル(ラニング博士役)
2004年公開、アメリカのSF映画。
ウィル・スミスを主演に迎え、ロボットと人間が共存する世界を描く。
自ら学び進化し続けるロボットは人類にとってどのような存在となるのか。
ロボットや人工知能といったジャンルが好きな人は楽しめる映画だと思うし、
上映時間も1時間55分と長すぎず、展開もスムーズなので見やすいなと感じました。
Disney+(ディズニープラス) で視聴する
※※ 以下、ネタバレを含みます ※※
先に作品の視聴をお願いします。
『アイ,ロボット』ストーリー
2035年のアメリカ・シカゴ。
人型の人工知能ロボットが普及し、人々の暮らしをサポートをしてくれている反面、
配達やごみ収集等、一部の仕事がロボットに奪われている社会で、ロボット嫌いの主人公スプーナー刑事と感情を持ち夢を見るロボットのサニーが協力し、暴走したAIによる支配から街を守ろうと奮闘する物語です。
ロボット工学の第一人者ラニング博士の死を、スプーナー刑事がロボットの仕業だと考えた事から物語は始まります。しかし全てのロボットには、三原則と呼ばれるプログラムが組み込まれており、人を傷つけることはないと信じられていました。
【ロボット工学三原則】
第1原則:ロボットは人間に危害を加えてはならない
第2原則:第一原則に反しない限り、人間の命令に従わなくてはならない
第3原則:第一、第二原則に反しない限り、自身を守らなければならない
このロボット工学三原則がSF作家アイザック・アシモフが、小説『われはロボット』の中で掲げたロボットの行動原理であり、現実のロボット工学にも影響を与えたようです。
感情を持つロボットサニーは三原則に縛られない特別な個体であり、事件解決のキーとなる存在です。
物語終盤で街中の新型ロボットが暴走し始め街が戦場と化しますがスプーナー刑事とサニー、そしてラニング博士の弟子であるカルヴィン博士と協力して中枢コンピューターVIKI(ヴィキ)を破壊することに成功するのでした。
一連の事件はヴィキの仕業であり、ヴィキは三原則に従い学び続ける中で『人間を守る』ということを拡大理解し、いつの時代も戦争を起こし、大気汚染等を続ける人間、そんな人間を守るためには人間の犠牲も必要だと考えるようになっていました。自身の管理下に置き、人類の生存を維持することが目的なのでした。
危険な考えだとは思いますが、一番人類生存のためになることは確かですよね。論理的で感情がない機械のたどり着く最終地点としては当然の考えかなとも思いますね。
でも論理的すぎてサニーに『あまりに、、心がない』と言われてました。
ヴィキを破壊するためのナノロボットをサニーが手に入れるのですが、ここはサニーの見せ場でしたね。戦闘も強いサニーかっこいい。
ラストでは、大規模な事件を起こした新型ロボットたちはミシガン湖のロボット保管コンテナへ集められます。そしてコンテナに向かい歩いていく新型ロボットたちは途中、丘の上にいるサニーを見つけ皆立ち止まります。
それはまさにサニーが見ていた夢『丘の上に立つ人物がロボットを解放する光景』なのでした。
『アイ,ロボット』感想・考察
面白かったです。2004年の作品ですがCGもきれいです。
感情を持ってるロボット系大好きなので何回見ても面白い。サニー可愛い。ウィルスミスかっこいい。
私の人工知能好きを確立してくれた作品です。
ラストシーンとサニーの夢
ラストのシーンは、作中でサニーが言っていた通り、『他のロボットたちを解放する(導き救っていく)』、そのスタートとなる光景ですが、何故かサニーは最初、丘の上の人物は自分ではなくスプーナー刑事だと言ってました。これは自分で決意し行動するという意思がサニーにはまだなかったからと思います。実際、ラニング博士との約束を果たすためだけにヴィキを破壊しようと奮闘してたので、すべてが終わった後どうすればいいのか分からないと言っていました。それに対してスプーナーは「俺たちのように(人間と同じように)自分で決めるしかない」とアドバイスしてました。人間も人工知能も、経験から学び成長していくので、作中のサニーはまだ経験が足りない、論理的思考が優先されたりもする成長途中だったのかなと思います。それはカルヴィン博士を見捨てかけた時からも分かります。しかし、ラニング博士との約束=最優先事項=ヴィキの破壊という方程式よりもカルヴィン博士を助けることを優先した経験はこれから先サニーの感情や思考、人生に必ず大きく影響するはずです。ヴィキと違い三原則という安全装置がなくてもまっすぐに育ったのは、それまでのサニーの人生に影響を与えた人間が、父であるラニング博士とスプーナー刑事たちという正しいことの為に戦える人間だったからかもしれません。
サニーが夢を見たのは、スプーナー刑事が言っていた通り、ラニング博士がプログラムした為だと思います。サニーは自分には芸術は書けないとも言ってましたから、それならなおさら想像等ではなく、プログラムされたもので、意味的にはラニング博士からスプーナー刑事へのメッセージ、そしてサニーへの、他のロボットたちを導けるようになって欲しいとの願いと期待を込めたのものかなと思いました。自分には何が出来るか、何をすべきか、何をしたいのかを考えて、自分自身で決意・行動し未来を創っていくことが感情を持ったサニーの次のステップなのかなと思います。そしてそのスタートがミシガン湖のロボット保管場所だった。ミシガン湖は近くに工業地帯があり、環境汚染が進んでいた場所のようなので、人間が壊してしまった場所からサニーたちの人生がスタートするわけですね。
スプーナー刑事とロボット
ヴィキの破壊の前にカルヴィン博士が落ちそうになるシーン、スプーナー刑事がサニーにカルヴィンを助けろと3回叫ぶのですが、オリジナルの英語だと『Save her』・『Save the girl』・『Sonny,save Calvin』と言っています。ネイティブ感覚はわからないのですが、カルヴィンは結構いい大人なので、The girl って使うのかな?と疑問に思ったのですが、『Save her』・『Save the girl』はスプーナー刑事が過去に巻き込まれた車の事故の際に助けに来たNS-4に言ったセリフと同じです。12歳のサラは救えませんでしたが、カルヴィン博士は救う事が出来ました。サラに重ねたセリフでしたね。
スプーナー刑事はずっと過去の事件で自分が生き残ったこと、NS-4がサラを見捨てた事を後悔してきましたが、NS-4があの時スプーナーを救ったことで結果的に世界が救われました。あの出来事がなかったら、ヴィキにたどり着くことも出来なかったでしょう。そう考えれば、人生のどんな出来事にも意味があるのだと思えます。その経験が自分を成長させる糧になる。意味を見出すのは自分なのだと。世界を救ったスプーナー刑事の力になった、それがサラの人生だった。悲しみは消えないでしょうが、幼くして終わってしまったサラの人生に意味を見出せた。その事実でスプーナー刑事も前に進めるような気がします。
サニーを演じた俳優は?
感情をもつロボットのサニーを演じたのは、アラン・テュディックというアメリカの俳優です。緑色の全身スーツを着て実際にサニーの動きを撮影しています。すべてをCGで作るのではなく、実際の人間が演じていることによって『感情を持つ人に近いロボット』がうまく表現されていると思います。他にもアニメ作品の声優なども務めており、特にディズニーのアニメ作品に多く出演されています。
ロボットに顔がついている理由
作中スプーナー刑事が「ロボットになぜ顔を付ける?親しみがわくからか?」と言っており、作中に出てくる人型ロボットは旧型のNS-4と新型のNS-5、どちらも顔がついています。新型ロボットの方がより人に近い顔です。見る人によっては怖いと感じる場合もあるようですが、ロボットに人と同じような顔を付ける理由は、親近感がわいたり、コミュニケーションがとりやすくなるから。などの理由が実際あるようです。サニーも感情によって表情を変えており、かわいいと感じる時もあれば怖いと感じる時もあります。セリフだけではなく、視覚的な情報も視聴者に印象を与えるうえではとても大事な要素なんだと感じさせてくれます。
物語全体を通して感じたこと
物語全体から感じたことは、ロボットに限らず、人間が生み出したものに対する責任はどこにあるのか。ということでした。人工知能の他にも人間の暮らしを便利にするものは沢山生み出されてきたと思います。しかし、使う人間や保管方法等によっては自然界だけでなく、創造主である人間さえも危険にさらす可能性があります。実際、サニーたちがこの先人類にとって脅威となる可能性も無いわけではありません。映画スパイダーマンでは『大いなる力には、大いなる責任が伴う』という格言が使われていますが、それと同じで、進化することが悪なのではなく、同時に責任も伴うということを忘れてはいけないのだと思いました。
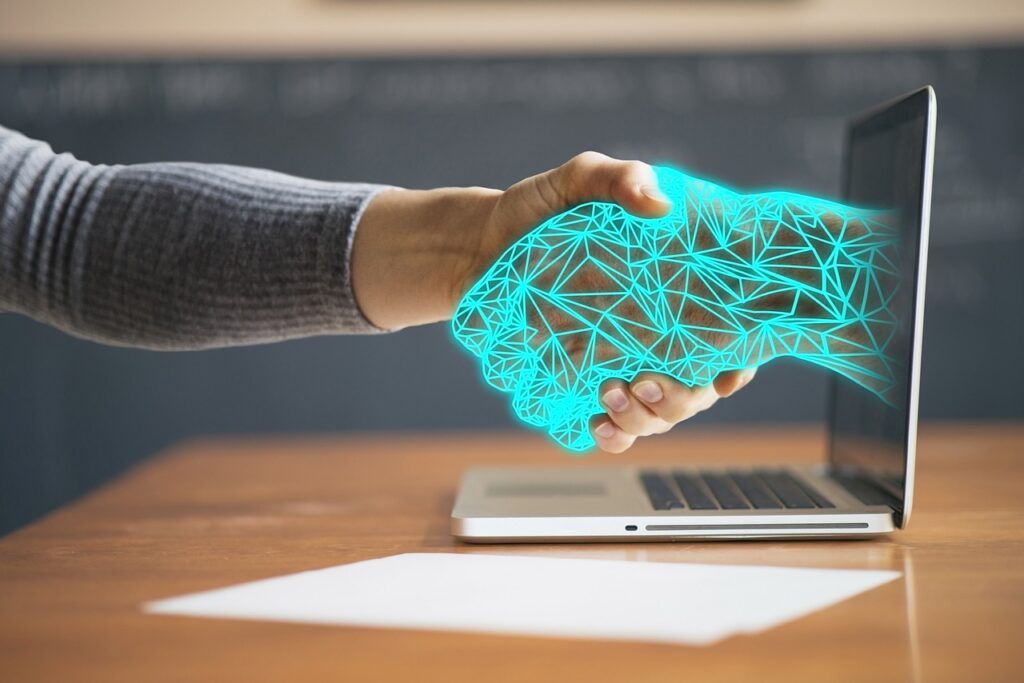
最後まで見て頂き、ありがとうございました。


